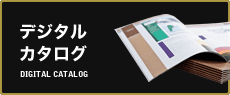1,一筋の光
1,一筋の光
丹波地方特有の濃霧にほのかな光明が射し込んでくるかのようであった。火の消えたような寂しさの続いた聖地・綾部にようやく明るさが戻ってきた。
明治41年に入り、出口王仁三郎(当時上田姓)は帰綾の決意を固め、組織づくり、宣教活動の本格的な準備に乗り出したのである。
聖師が綾部を離れたのは明治39年9月、京都に開設されたばかりの皇典講究分所に入学するためであった。
当時、教団は政府の執拗な干渉を避けるため、静岡に本部を置く公認の結社である稲荷講社の分会という形をとり、金明霊学会の名で布教活動を行っていた。旧帝国憲法下では政府公認でなければ宗教活動は許されなかったのである。
その頃、聖師は幹部から「悪神がついている」として「綾部にはおれない有様」(おさながたり)であった。聖師は当時のことを「窮乏と圧迫の中に住みながら前途に望みを抱へ書を書く」「著書は皆夜具をかぶりて夜の闇に執筆したるものばかりなり」と懐古している。
「霊の礎」「筆の雫」「道の栞」など現在残っている教典はこうした中で当時書かれたものである。その他にもかなりの書があったが、幹部から漢字まじりの文章は「外国のやり方」であるとして焼却されたという。
屈従の日を送っていた聖師は、神職の資格を得て宗教活動の合法化の道を得ようと綾部を離れ、他日を期そうとの決意を固めた。
すでに35才。妻子ある身ではあったが、明治39年9月、同分所の一期生として入学したのである。
明治37年に日露戦争が勃発し、出口なお開祖が明治25年から予告、警告されていたお筆先どおりの展開となって、信徒は勇み立った。
しかし、世はまっ暗がりだとして昼間から提灯をつけて歩きまわるような正直一途な信仰集団は、いつの間にか社会から乖離した存在となっていった。日露戦争によって立替え立直しがあると強く信じていた信徒は戦後しだいに離反していき、警察の干渉もきびしく、とりわけ聖師が綾部を離れたこともあって教団は衰退を余儀なくされていったのである。
明治40年3月、皇典講究分所を優秀な成績で卒業した聖師は4月に京都府の神職尋常試験に合格した。
翌月、京都府から別格官弊社建勲神社の主事に補せられたが、信徒がつぎつぎと訪れるので宮司から官弊社の尊厳を傷つけられると叱責されることも多く、同年12月辞任した。
建勲神社を去った聖師は京都の伏見稲荷山にある御獄教西部教庁の主事に招かれた。ほどなく中教正に任じられ、大阪大教会長として生玉の御獄教大教会詰に栄進した。
聖師はこの間にあって、宗教界の実態にふれ、教団組織や教会経営を体験し、一方では社会的視野をひろめていった。
大阪にあっても、聖師は絶えず信徒との連絡をとり続けていたが、すでにこの頃には窮迫のどん底にある綾部に帰る決意を固めていた。
当初は月一回程度の帰綾ではあったが、湯浅斎次郎などの支援を得ながら着々と教団再建を図り、8月には金明霊学会を改めて大日本修斎会を創立した。
開祖から「今後他出相成らぬ、綾部に居るように」と厳命された聖師は12月、御獄教を辞任して綾部に帰り、教団の組織化に専念することとなった。