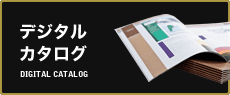11,第二次大本事件
第二次大本事件
尊師が誌されているように昭和八年から十年にかけて天声社は組織的にも整備され、総務部、営業部、雑誌部、代理店部、倉庫部、工場経理部、文選部、欧文部、鋳造部、製本部、銅版部(旧明鏡館)、写真部(旧智照館)などに分かれていた。幹部は高木鉄男を中心に中山勇次郎、土井三郎、河津雄次郎などが補佐するという陣容であった。
工場は木造一部二階建で、その二階は聖師の部屋にあてられた。聖師はたびたび訪問されてはその部屋から熱心に作業をご覧になり、社員はそれをまた喜びとしていた。
仕事はそれぞれの分担に従って進められたが、例えば紙型場では当時まだ自動圧搾の技術が確立していなかったため、毎日のように雁皮紙を貼り合わせ特殊ブラシで叩き紙型をつくった。再版の際にはこの紙型から鉛版をつくり印刷場へまわされた。
さて、昭和神聖会結成以来その活動はいやがうえにも盛り上がり、またたく間に日本全土にひろがっていった。
しかし、一方では当局が着々と秘密裡に膨大な大本の刊行物を集め、調査に乗り出していた。
当局にとって皇道大本は国家神道体制の枠からはずれた異端な存在だけにとどまら破壊された天声社工場ず、国家権力にとって危険な存在とうつるようになってきた。昭和十年の初めから極秘に進められた弾圧の準備は、十月にはほぼでき上がった。その至上命令は「大本を地上から抹殺する」ことであった。
昭和十年十二月八日、約五百名の警官隊は綾部、亀岡の両聖地を急襲し、尊師をはじめ幹部を検挙した。また聖師は巡教中の松江市で検挙、京都市に護送して中立売署に留置した。松江での大祭を終えて綾部に帰った二代教主も、翌十一年3月に女性でただ一人検挙された。
弾圧は本部に限らず全国の地方機関にも及んだ。その数は百ヵ所を超え、各地の幹部も次々と検挙されて六十一名に達した。
有力新聞を始めとするマスコミは一斉に「邪教大本」「国賊出口王仁三郎」と糾弾、官民あわせて大本攻撃を繰り広げた。
昭和十一年三月十三日、聖師ら教団幹部八名は「治安維持法違反」と「不敬罪」で起訴された。
その時を待っていたかのように、解散命令と建造物破却命令がだされ、国家権力は一挙に一宗教団体におそいかかってきた。
大本への弾圧は苛酷を極めた。昭和十一年五月には裁判の開始もまたず両聖地の施設の破壊がはじまった。
もとより天声社は事件当日より操業ストップしていたが、昭和十一年四月二十四日には、工場の倉庫に在庫していた用紙全てが京都市内の洋紙店へ六千円で売却された。また印刷機会も京都市内の印刷会社へ約一万円で売却することが決まり、5月10日より解体、搬出がはじまった。
さらに、五月五日には休刊となっていた「神の国」「瑞祥新聞」「真如の光」「エス文OOMOTO」などの機関誌が廃刊処分となった。
一方、工場は五月十一日から床板、天井の撤去がはじまった。この作業も急ピッチで進められ、六棟すべてが他の神殿や建造物とともに解体、破却された。当時、工場や売店にあった約八万四千冊の書籍や機関誌も、すべて神苑内の窪地に積み上げられて焼却された。その炎は夜空を焦がし、余燼は一ヵ月余りもくすぶりつづけた。亀岡の工場は解体後亀岡町営住宅として、旧第一天声社の工場だった神光社は綾部商工会へ売却されて、再利用された。さしもの山陰一をほこった新鋭の印刷工場は、無残にも地上から姿を消したのである。
第二次大本事件当時の天声社工場は印刷工場四棟、写真部、銅版部各一棟で、延建築面積は約一千六百平方メートル。設備は菊判(三十二頁掛)輪転機一台・菊判(十六頁掛)印刷機三台・四六判(十六頁掛)印刷機三台・菊判(八頁掛)一台・四六版(八頁掛)三台・四六版(四頁掛)三台・ビクトリア型一台・四六版全断裁機三台・針金綴機二台・糸綴機一台・活字鋳造機五台・紙型機一台・鉛版機二台・自動研磨機一台。それに活字をつくる字母としては三号、四号、五号、六号、一二ポイント、九ポイントルビ付き、欧文などであった。この他文選ケースには初号活字から大本特有の呼び方をつけたルビ付きの各種文字がそろっていた。
定期刊行は「神の国」「真如の光」「昭和」「明光」「瑞祥新聞」「エス文OOMOTO」エス文「緑の世界」ローマ字誌「日本」であった。
事件によって、社員の大半は命令によって帰郷を余儀なくされたが、なかには京都市内や地元で就職、あるいは入隊する者もあった。
昭和一三年、京都地方裁判所の第一審が開廷して以来、長年にわたる法廷での闘いが繰り広げられた。それは厳しく苦しい闘いではあった。昭和一七年七月、第二審の判決で一審判決がくつがえされ、不敬罪は有罪であったが、治安維持法が無罪となって新局面を迎えた。
聖師、二代教主、出口宇知麿は八月七日、保釈となって六年八ヵ月ぶりに亀岡へ帰った。
この後も裁判は大審院に持ち込まれ、検察側と弁護士側の激しい応酬が繰り広げられた。
結局、大審院の判決は不敬罪を有罪としたが、それも翌月の昭和二十年十月十七日の大赦令で、これらすべては解消した。