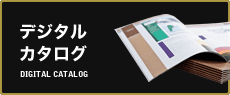2,蘇る活気
蘇る活気
聖師が綾部を離れていた明治40年前後の大本は、開教以来もっとも衰微した時代であった。
出口一家は三度の食事にも事欠く有様で、時にはカシの実を拾って団子にし飢えをしのぐといったこともあり、家計をきりもみする出口すみ子二代教主の苦労は筆舌に尽くせぬものがあった。
開祖の「お筆先」に必要な筆墨はおろか、和紙を買うのにも四苦八苦で、二代教主や幹部は縄ないの手仕事をしたり、力仕事に出てやっとその日の生計をたてていた。
こうしたなかで、聖師の帰綾は教勢回復の大きな機転となった。湯浅斎次郎、梅田信之、吉田竜次郎といった有力な信徒のバックアップもあったが、その活動は目をみはるものがあった。
明治41年12月8日の秋季大祭には参拝者が約100名をかぞえた。前年の秋季大祭がわずか20名ばかりの参拝者であったことからみても、聖師の帰綾がいかに大きな活力となったかをうかがい知ることができる。
聖師は明治41年9月、教団としては最初の機関誌「本教講習」(月刊)を発行、当時としては画期的ともいえる文書宣教に着手した。以降、大本は積極的に印刷、出版に力を注ぎ、今日それが教団の輝かしい伝統となって引き継がれている。
聖師が印刷に注目したのは皇典講究分所に在学中、文芸クラブ「秋津会」の幹事に推され、同人誌「このみち」の主筆となって文筆活動をしたことが契機になったといわれる。
ラジオ、テレビなど今日のようにマスメディアが発達していなかった時代、新聞や雑誌といった印刷物が思想伝達の主役であった。
印刷の威力を体得した聖師は、以後の宗教活動でこの情報手段をフルに活用、展開していった。
当時、聖師は有力な信者であった吉田竜次郎にあて「茲に看過すべからずは印刷部の設置に候が」と述べて「まず活字を用意するため、七、八百円の融資を受けたい」との信書を出している。この時には実現しなかったが、聖師のこの熱意は数年後に実現をみることとなった。また印刷の歴史や技術についても造詣が深く、後年次のような見解を発表している。(大正12年「神の国」2月25日号)
「我輩の肉体の一方の側面に二本乃至三本の窪んだ処がある。人間は之を名付けてネッキと呼んでいるが、之は文字の字体を見分け易からしむる為に作ったものだ。また他の側面に円形の浅い窪所があるのもあって、之は我輩の臍なのであるが、人間は勝手に之を丸釘又は鍼標と名付けて、時によっては製造所の名を示すよすがとして居る。それから普通の新聞や雑誌に用いらるる活字は明朝の流れを汲んだものが大部分を占めているが、そのほかに清朝の系統もあれば、我輩の如きゴジック系のものもあるのだ。我輩の仲間の大小は日本では本木昌造という人が定めたものを基とし、初号の下に一号から七号までの区別がある。近年八号が生まれたけれども未だ広く天下の愛翫を受くるに至っていない」
「印刷の元祖は世界を通じて勿論木版であった。我が国にては堀川天皇の寛治年間に既に活字版をもって印刷した事実があったけれども其盛んになったのは文禄慶長の役に我将士が朝鮮活字を多数捕獲して以来のことである。安政年間、大阪に一活版工があってM数千の活字を抱えて巡回印刷業を始め、各地を旅行して其土地々々で人の求めに応じて適宜に印刷し、大に人気を博したことがある」
「現代の人々はややもすると世界の文化がどうの、科学的文明の進歩がどうのと、世界の開化発展は丸で人間のみの努力によって成っているように宣伝しているが、何ぞ図らん人類今日の文化は我輩活字に負う所が実に多大なものである。。世界各国文明の程度は我輩や先輩の努力に正比例しているといって差支えない。人間は万物の霊長だなどといっているが、人間社会より一度我々活字の影を没したとしたら、ドンナ悲惨なものだろう。我輩が世界的同名罷業でもして見ろ、天地は暗澹として咫石(しせき)を弁ぜざるの状態を現出するだろう。古今聖賢君子の言説を始めとし、文学に、美術に、宗教に、実業に、教育に政治に或は産業に、其他社会的現象の一切に於て我輩の献身的努力がなかったならば、果してよく現代の進歩をみたであろうか。云々・・・」
以上をみても聖師が印刷をどのように高く評価していたかを理解することができる。
聖師の帰綾によって、大日本修斎会の活動は活発化したが、財政状態は相変わらず困難をきわめ、自ら先頭に立って資金の調達に奔走しなければならなかった。さらに警察の干渉は依然として厳しく、せっかく8月に創刊した「本教講習」も4回発行しただけで、その年の12月には廃刊のやむなきにいたった。