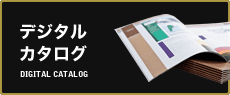4,発展する教勢と印刷体制
発展する教勢と印刷体制
立替え立直しの切迫がお筆先によって頻繁に示され、また第一次世界大戦の勃発という社会情勢の中で、一時中断を余儀なくされていた文書宣教が再開されることとなった。
まず大正2年4月には綾部町本宮町小宮新宮17に印刷所が開設され、藤本薫を主任に、四方熊太郎(四方平蔵長男)が配属された。
印刷所とはいえ木造の家屋で、一階を印刷場、二階を製版場とした。聖師は「原稿を書くのはじゃまくさいと、自ら文選、植字をされ、印刷、製本をして、帯封まで書いて、これと思われる人に発送されました」(岡崎邦夫「おほもと」誌昭和53年1月号)という一人で何役もこなす頑張りだった。
大正3年8月には「直霊軍」に代わる機関誌として「敷島新報」を創刊した。初めはB4判の月刊(毎月15日発行、1部3銭)であったが、のちこれをB5判月2回発行とし、さらに旬刊と発展していった。当初の設備は活字と速水鉄工所製の足踏印刷機一台などささやかなものであった。この資金(200円)の大半は宇治に住む信徒、辻弥太郎の献金によるものであった。
岡崎も小学校が終わると四方熊太郎の手伝いをさせられたというが、その後、四方は主任となり、工場の中心的存在に成長していった。しかし、惜しくも大正9年、まだ22歳という若さで昇天した。四方は事実上、天声社の社員第一号で、創業時における最大功労者の一人であった。
大正9年5月30日号の「大本時報」には彼を偲んで次のような哀悼文が掲載された。
四方熊太郎氏の死を悼みて
(少年隊) 若水生
あゝ、鶴髪童顔の老爺四方平蔵先生の嫡子、四方熊太郎氏は遂に逝けり。余は茲に逝きし氏の経歴を顧みて転た思慕の情に耐へず。氏は実に現印刷科の元勲なり。現印刷科が今日の発展致せしの効は半ば之を氏の努力に帰せざるべからず。噫氏はつひに逝けり。然れ共氏の残せし功績は永遠に消えず。惟るに、大本最初の機関誌『本教講習』に『丹洲時報』に『直霊軍』に『敷島新報』に『神霊界』に『綾部新聞』に尊き努力の跡は、ありありと所在に氏の惨苦を物語るを見ずや。初めて大本に印刷所の設置せらるゝや、歳猶幼なる氏は決然身を提して斯業に従事し活字の不足も、人手の不如意も、機械の不完全も、器具の不十分も、場所の不便も、総て突破撃退して、意に介せず。寒き冬の日も、梅干に似たる火に手を翳しつつ、氏のみ一人居残りて幾日徹夜せし事よ。さあらず共日毎に夜業を欠かさずして十二時を超ふるを常とし朝は未明に起き出で、箒を持ちし後小暗きランプの下に往きて又、いとも冷たき活字を片手に東天の白み初むるを見るが氏の日課なりき。いたく暑き夏の日も、蒸々たる工場に篭りて曽て昼眠せし事もなし。春花も秋月も由来氏と関係を断ちにしや、十年一日の如く、孜々として只管機関誌と相伴ふこと形影相随ふが如かりき。
四時欣々日夜悠々として迫らざる平蔵翁にして斯子あり、氏は翁の性を享けて実に霊関相承の父子なりき。
而して氏の恒に怡然として、笑に溢るゝ面を見れば、無量の神徳を受けつつあるを思はしめ常に赫々たる光明の、赤き血踊れる氏の胸に照り映ゆるを想はしむ。氏の抱負や如何に大なりけむ。其希望や如何に雄々しかりけん。然れども、この雄々しき氏の魂に、伴へる肉体は余りにも病弱なりしなり。氏の勤労の余りに激しきを見て、窃かに氏の身を気遣ひ、再三休養の何なるを説きし人幾人なりしならむ。されど氏の赤誠はこの忠告を甘受することを敢へてせず、身心を捧げて工場に殉ずるを期せるが如し。云々・・・。
翌週の6月6日発行第100号の大本時報には「綾部だより」の欄に葬儀の模様を掲載している。